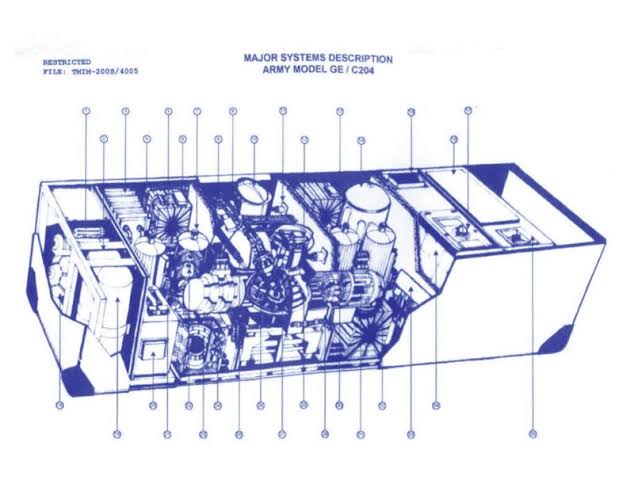The Smiths ザ・スミス 映画 イングランド・イズ・マイン公開に寄せて
- 2019.07.10 最終更新日
- 2019.07.11
- 音楽

©︎The Smiths
ザ・スミスのモリッシーとジョニー・マーの物語の映画が最近公開されている。
このところクイーンといい伝説のバンドの映画化が流行りなのかな、でもスミスは大ヒットは望めないな…。絶対ファミリー向けの映画にならないのは確かだ。
少なくとも自分は家族と見たくない。
何故ならスミスの音楽自体が僕の隠しておきたい青春時代の暗部と重なっているからだ。
はっきり言おう。
僕はスミスが大好きだ。
これは隠しておきたかったのだがこの記事を書き始めたからには仕方がない。
色々書いていたら隠しきれるわけがない。早めに白状してしまおう。
今まで生きてきた中で一番多くの回数を聴いたバンドかもしれない。そして今でも無性に聴きたくなる時がある。
でもスミスが好きだなんて他人には絶対言いたくない事なのだ。
今でこそミュージッシャンズミュージシャンとして正当な評価がされてきた感があるが、90年代は口が裂けても大好きなんて言えなかった。
スミス好きという事は、わたし変人です、と言ってるのと同義だった。
だって、ホモを公言してて、
男同士で二階建てバスに突っ込まれて心中したいなんて言ってる歌とか、
些細な軽口を後悔しまくってる歌とか、
芳ばしい肉の香りが漂う家族の食卓を虐殺の処刑場の香りだ!
なんて言って補聴器を付け、恐ろしくなよなよした気持ちの悪いモリッシーダンスをしながら歌っているバンドなんて、
かっこ悪いを通り越して、悪趣味としかいいようがない!!
と思いながら聞いてるうちに、
気づけば僕はスミスを聞かないと生活出来ない、スミス中毒の人間になってしまっていた。
僕の青春時代の比較的大きな割り合いがスミスで埋め尽くされていった。
僕は青春時代、人並みにも悩んでいた。
悩みまくっていた。
そしてその憂鬱な気持ちに何故だかスミスがよく馴染み、染み込んでいった。
マッチョイズムを恨むかのように、男として社会人として普通の人ならタブーにしてしまう所、恥ずかしくて絶対秘密にしないといけない所をひたすら歌いあげるモリッシー。
普通の人だったら、カッコ悪くて必死になって隠す世界を100パーセント晒けだしている所が逆説的にロックであり、イメージからは程遠いもののまさしくパンクだった。
ロックが、音楽が、
人間の魂を解放していく行いであるとすれば、彼ら程、人間の魂の自由を歌いあげ、社会の歪んだ「常識」にがんじがらめにされている若者の魂を救ったバンドはいなかった。
いい学校に行って勉強出来る人間が優れている。
恋愛し結婚し仕事をするのが人間の道。
社交的で友達がいる人が優れている。
異性が好きなのが正常。
オシャレをするのが若者の正しい姿。
アメリカ文化はカッコいい。
古いものより新しいものが優れている。
数百年前の古臭い文学より今の音楽の方がかっこいい。
MTVが全盛期の80年代前半。
街ではコマーシャリズム全開のアイドルのようなポップグループやテクノグループがもてはやされていた時代。
オタクが最も生きづらかった時代。(オタクという言葉すらもなかった時代)
こうした世間の常識全てにおいてスミスはNOを突き付けた。
本当はそれ以外のものの方が尊い事を歌いあげた。
くだらない常識という世界の外にスミスはいた。
スミスの音楽の中では、それこそが全てで、真実がそこにあった。
無意識の内にこうした世間の「常識」に囚われ、なんらかの要因でこういった「常識」に乗れず、行き場を失った、さ迷える若者達は熱狂的にスミスを支持した。
スミスを聞いてその世界に入りこんでいくと、なんていうんだろう、こう世界が「裏返る」瞬間を感じる事がある。
まさしくそれが本当のロック、いや音楽の姿にほかならなかった。
イギリスではスミスの名を遺書に残し自殺をする人が多数現れた。
報道陣に追求され、スミスのボーカル、モリッシーはこう言った。
「責任なんて感じない、本当に。彼らの人生の最後にスミスがあっただけでも幸せだったと思うよ」
スミスみたいなバンドは
スミス以外、後にも先にも出て来ていない。
精神的にも音楽的にも似てるバンドを探すのは難しい。
影響を受けてるバンドは沢山いる。でもスミスみたいなバンドはいない。
これだけ影響受けている人が多いのにスミスに似てるバンドがいないのは不思議だ。
恐らくスタイルを真似る事が不可能な種類の音楽なのだ。
スミスには天才が2人いる。ギターのジョニー・マーとボーカルのモリッシーだ。
ジョニー・マーは早熟で努力型の天才。
10代にしてスミスの曲を書き、異常な程のギターのテクニックがあるが目立つようなソロギターや派手なフレーズは決して弾かない。常に奇妙に美しい旋律をボーカルの背後で奏でる。
僕はマーの職人肌のいぶし銀的なギタープレイが大好きだ。
モリッシーは誰にも気づかれなかった天才。
モリッシーは楽器も作曲も出来ない。
無名な家に引きこもりがちのオスカーワイルドに傾倒する文学青年の歌声は、
ジョニー・マーの奏でるギターの旋律に乗った瞬間、天才として人々の注目を集めた。
そして、上記で書いた、常識に囚われないスミスのメッセージ性というのはモリッシーのメッセージに他ならない。
初期のスミスサウンドは強烈だ。
ジョニー・マーの弾く独特のコード進行の、メロディとアルペジオの中間の様なギターフレーズに、モリッシーの詩の朗読の延長にあるような、古代民謡のような、メロディを歌いたいんだけどメロディにならないような歌が絡みスミスサウンドとなる。
これはウィリアムという曲
「退屈な街に雨が降る この街は君を駄目にしてしまう」というリフが終わると
「ウィリアム、ウィリアム、本当になにも無かったんだ」と突如男の名前を連呼して弁解する曲(笑)
それにしてもモリッシーが歌う詩の世界は独特だ。Cemetry Gatesという曲を紹介しよう。
“Cemetry Gates”
“墓地の入り口”
A dreaded sunny day
ぞっとするくらい晴れた日に
So I meet you at the cemetry gates
墓地の入り口で君と待ち合わせ
Keats and Yeats are on your side
君の隣にはキーツとイェーツ
While Wilde is on mine
でも僕にはワイルドがいる
So we go inside and we gravely read the stones
僕らは中に入り、厳かに墓碑銘を読み上げる
All those people, all those lives
ここに眠る人々、彼らの人生
Where are they now?
今彼らはどこにいるのだろう?
With loves, and hates And passions just like mine
愛と憎しみ、それと僕らと同じように情熱を抱いて
They were born
彼らはこの世に生まれ
And then they lived
人生を生き
And then they died
そして死んでいった
It seems so unfair
それが不当なことみたいで
I want to cry
僕は泣きたくなる
You say : “‘Ere thrice the sun done salutation to the dawn”
君は言う:太陽が三度沈む前に、夜明けに挨拶せよと
And you claim these words as your own
それが自分の言葉だと君は言い張るけど
But I’ve read well, and I’ve heard them said
A hundred times (maybe less, maybe more)
僕は物知りさ、これまでにその言葉は百回も聞いたよ(それ以下かもしれないし、それ以上かもしれない)
If you must write prose/poems
もし散文や詩を書くならば
The words you use should be your own
自分の言葉で書かなきゃね
Don’t plagiarise or take “on loan”
盗用や借用はいけない
‘Cause there’s always someone, somewhere With a big nose, who knows And who trips you up and laughs
When you fall
いつだってそういう事を嗅ぎつけて
君がヘマをした時、揚げ足をとって笑う奴がいるのさ
Who’ll trip you up and laugh When you fall
ヘマをした時揚げ足をとって笑う奴
You say : “Ere long done do does did”
君は言う:やりまくる、やる、やっちまった
Words which could only be your own
これは君の言葉だろうと思ったけど
And then produce the text
From whence was ripped
君はそのセリフの
引用元をさらけ出した
(Some dizzy whore, 1804)
(ある浅はかな娼婦の作品、1804年)
A dreaded sunny day
ぞっとするくらい晴れた日
So let’s go where we’re happy
こんな日は幸せに浸れる場所に行こうよ
And I meet you at the cemetry gates
墓地の入り口で君と待ち合わせ
Oh, Keats and Yeats are on your side
君の隣にはキーツとイェーツ
But you lose
でも君の負けさ
‘Cause weird lover Wilde is on mine
だって僕には奇妙な恋人、ワイルドがついているもの
Sure!
そうさ!
2人の天才がいるバンド
という事で、イギリスではビートルズの再来なんて言われ、
スミスはよくビートルズと比較されたらしい。
でも僕はまるで違う種類のバンドだと思う。
ビートルズのジョンとポールは2人とも楽器が出来るし歌も歌え、曲も作れる。
1つの曲をお互いのアイディアを入れてカタチにしていく、後期はライバル的な関係もあり、お互い切磋琢磨し新しい世界を切り開いていった。
対して、スミスのモリッシーはまったく曲は作れない、ただしジョニー・マーの奏でるギターの旋律の上でだけ彼は歌を創る事が出来る。
マーは独創的でテクニカルな曲は作れるが、歌は作れない。
曲にメッセージを込めることは出来ない。
ホントに2人で1つになれる稀有なコンビだった。
スミスの奇妙な共生関係はどちらかが音楽的に成長するか相手に飽きてしまった瞬間崩れてしまう危ういバランスの上で成り立っていた。
スミスがデビューしてたった四年で解散してしまったのはある意味必然だったのかもしれない。
モリッシーはアカペラでも歌えるくらい歌が上手くなった。
マーはあまりのモリッシーの音楽的な柔軟性の無さと独特すぎる世界観に嫌気がさしていた。
社会的弱者いわいる「マイノリティー」の世界を核にした音楽を作り始めたのはおそらくスミスが始めてで、
スミスが解散したのは、もう30年以上も前の事なのだが、
映画化の流れといいスミスもといモリッシーの「常識」やメインストリームの外の方こそ豊かな世界があるというメッセージの真価がようやく理解されつつある時代になったのかもしれない。
最後にスミスの映画の、監督のインタビューが面白かったのでリンクしておきます。
それと、僕のお気に入りの曲もリストアップしておきます。
(選びきれなくてたくさんになってしまった。。)
-
前の記事

アトピー性皮膚炎のおかげでペスクタリアンになってしまった 2019.07.07
-
次の記事

アーティストの政治的発言について 2019.07.14